基調講演
「開発、保全に第3の視点“暮らし”を」
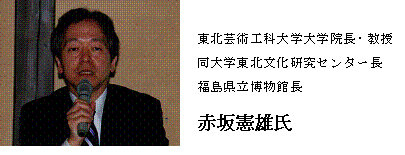
「五月雨を集めて早し最上川」。芭蕉が最上川の情景を表現した、とても良い句です。私は、この最上川のほとりの村々を90年代に10年ほど掛けて、聞き書きをしながら歩きました。その記憶をたどりながら、川のかたわらに生きてきた人たちの思いなどを語らせていただきます。
柳田國男の『豆の葉と太陽』の中に、「川」というエッセイがあります。この中で柳田は、川をめぐって、上り下りの縦の関係があると同時に、もう一つ、川には横の関係があると言っています。
また、こんな一節があります。
「要するに、流れと人間との交渉が、最近著しくその様式を変えようとしているのである」
川と人間の関係が非常に変わってきた。柳田の時代からさらに70年を経て、われわれの目の前にある川、そして人間とのかかわりといったものは、もっと大きく変わってきたと思います。
帆柱をかけた舟がコメや紅花(べにばな)を積んで川を上り下りする風景は、昭和30年ごろまで最上川のほとりの村々には確実に残っていました。そのころ、最上川の中流では亜炭(あたん)を積んだ航海舟が行き来していたのです。それは、川の流れに沿って人々が縦の利用をしているということです。
それに対して横の利害は、流域に暮らす人たちが田んぼに最上川から水を引き入れる。その人たちは大抵、川のほとりで暮らしていますので、簗(やな)をかけたり、川漁をしていることが多い。そして水力発電、ダム、汽車といったものが横の利害や関係として交差するのです。
明治時代に交通が陸上へと大きく転換する前は、日本の交通の大動脈は海であり川でした。河川交通なしに大きな荷物を運ぶことはできませんでした。川がハイウエーであり交通の大動脈だったことはわれわれの記憶の中から消えてしまっていますが、日本の歴史をひもといてみると、陸の交通と海や川の交通が交互に出てきます。
また、大石田の辺りはかつて、非常に栄え、周辺の農村から借金のカタに次々に田畑を集積していった人たちが何人もいました。その人たちは、近世江戸時代には豪商として最上川の舟運にかかわりながら財産を蓄積していったのですが、明治になって時代が大きく転換し、もう舟運の時代ではないというのが見えたときに一気に転換していったのです。
彼らは、周辺から田んぼを集め、10年、20年で巨大な地主になりました。農民ではなく、豪商といういわば川をめぐる縦の利害に依存しながら金持ちになった人たちが、逆に今度は横の利害の代表である農業に進出して巨大な地主になったのです。
われわれの時代には、川の漁や舟運で暮らす人たちは全く姿を消しました。川と人間のかかわりということを考える時に、90年代の聞き書きの中で、かすかな記憶としてたどることはできましたが、もはや目の前にある最上川は人間との生々しい関係の中で守られている川ではありません。
むしろ川は一度死んだという風に考えて、そこから立て直すしかないのでしょうか。自然の景観を守るとか、自然の法とかにかかわって、私は村歩きをしながら苛立つことがしばしばありました。常に、「開発」か「保護・保全」という二分法で決めようとする。
けれど第3の視点があるはず。それは、その自然のかたわらに暮らす人々の暮らしであり、生業(なりわい)であり、思いであり、信仰であり、開発か保護・保全かではなく、生活や生業という第3の視点を置いて、その三角の関係の中で考えていく必要があるのではないかと思うのです。
美しい風景のかたわらには、その風景を守り育ててきた人がいます。美しい村について、しばしば語った柳田は、「風景を植える」という言葉を使いました。風景というのは、自然に放っておいて勝手に成長するものではなくて、そこに人間がかかわってつくっている、人間がかかわったという歴史が必ずあるということです。
一方で、われわれには風景や景観、自然を守っていく義務と責任があるということです。人間がつくったものだから何をしてもいいだろうというのではなく、人間がかかわりながらつくってきた自然は、これからもかかわり続けながら守っていかなければならないということだと思います。
今、川や里山の景観が壊れつつあります。そこにわれわれは、どのようにかかわることができるのかを考えていく必要があるのではないでしょうか。